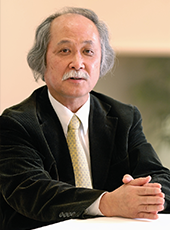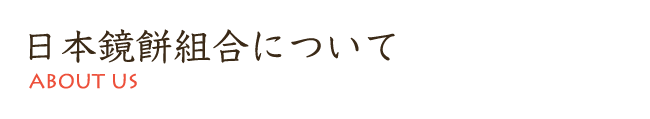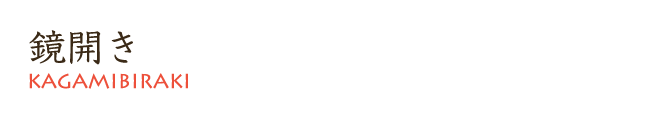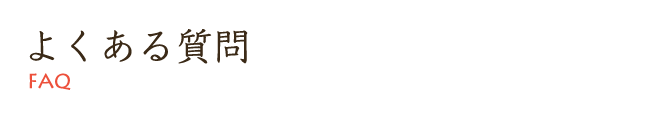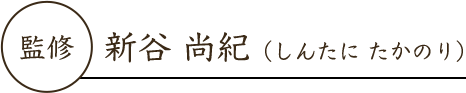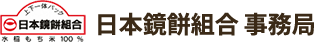お雑煮とは、年神様に供えた餅を神棚から下ろし、野菜や鶏肉、魚介などで煮込んで作る料理で、その起源は室町時代までさかのぼることができます。
安土桃山時代に編纂された「日葡(にっぽ)辞書」(1603年刊行)に、お雑煮は「正月に出される餅と野菜で作った一種の煮物」の表記があります。
元日にお雑煮を食べる風習が庶民の間に定着したのは元禄以降。長い年月をかけ、お餅の形や調理法、だし、味付けに地域性が生まれました。
新しい年を寿ぐお雑煮には、ふるさとの香りが漂います。日本の伝統的な正月料理であるお雑煮は、実に地方色豊か。それだけではなく、家庭によっても異なり多種多様のお雑煮があります。大まかに分けると、関東では角餅を焼いた澄まし汁仕立て、関西は丸餅をゆでて味噌仕立てが多く、中に入る具もその土地でしか味わえない山の幸、海の幸が使われていたりします。しかし、どんなお雑煮でも主役はお餅。伝統のお雑煮や変り種のお雑煮を、どうぞお試しください。
- 鶏肉はそぎ切りにしておく
- 小松菜はゆでて5~6cmの長さに切る
- かまぼこは熱湯を通してから8枚に切る
- だしを煮立て、鶏肉を入れて弱火で煮る
- 4に塩、醤油で味をととのえる
- 餅は焼いて椀に盛り、温めたかまぼこ、小松菜を入れ、
その上から鶏肉と汁を注ぎ、上に短冊に切った海苔を載せる
材料(4人分)
- 切餅4個
- 鶏肉80g
- 小松菜120g
- かまぼこ
- 海苔1枚
- だし3カップ
- 塩、醤油適宜
- 鶏肉はそぎ切りにしてさっとゆでる
- 里芋は鶴の子、大根は日の出、人参は亀甲に切り下ゆで。
小松菜はさっとゆでておく - だしに材料を加えさっと煮て、味噌をとき加える
- 椀に湯の中で軟らかくした餅と具を盛り、
汁を注ぎ柚子を添える
材料(4人分)
- 丸餅4個
- 鶏肉100g
- 里芋4個
- 人参50g
- 大根50g
- 小松菜100g
- だし3カップ
- 白味噌90~100g
餅の形、汁、具などに特徴のある、各地の代表的なお雑煮を紹介します。普段のお正月に食べているお雑煮とはちょっと違うかもしれません。
- わらび、ぜんまいは4cm、せり2cmの長さに切り、姫筍は斜め切り、人参は輪切り、鶏肉はそぎ切りにしてゆでる
- だしに1を加えて煮て、塩、醤油で味をととのえる
- 焼いた餅を椀に入れ2を注ぐ
材料(4人分)
- 切餅4個
- わらび40g
- ぜんまい40g
- 姫筍40g
- ふき20g
- きのこ40g
- 人参40g
- 鶏肉80g
- せり20g
- だし3カップ
- 塩、醤油適宜
- 大根は短冊切り、ごぼうは千切り、人参、里芋は回し切り、
ねぎは5cm幅の輪切り、豆腐はさいの目、こんにゃく、
塩鮭を短冊に切り、ほうれん草はゆでて4cmくらいに切る - 大根、ごぼう、人参、里芋、こんにゃくはさっとゆでる
- 鍋にだしと2を入れ煮、軟らかくなったら塩鮭を入れ、塩、醤油で味をととのえる
- いくらとほうれん草を加える
材料(4人分)
- 切餅4個
- 大根100g
- ごぼう50g
- 人参40g
- 里芋2個
- ねぎ1/2本
- こんにゃく1/4丁
- 焼き豆腐1/4丁
- 塩鮭の切り身60g
- ほうれん草75g
- いくらまたは筋子75g
- だし4カップ
- 塩、醤油適宜
- 大根は半月に切る
- だし汁に大根を入れ軟らかくなるまで煮て、ブリの切り身とはまぐりのむき身を加え、塩、醤油で味をととのえる
- 椀に焼いた餅を盛り2を注ぎ青菜を添える
材料(4人分)
- 丸餅4個
- ブリの切り身2切れ
- はまぐりのむき身4個
- 大根100g
- 青菜100g
- だし3カップ
- 塩、醤油適宜
- 塩ブリは塩抜き、鶏肉はそぎ切りにする
- 大根は短冊、人参は輪切りにしてゆでておく
- かきと三つ葉はさっとゆで、かまぼこは5mmの厚さに切る
- だしに1を加えて煮て塩、醤油で味をととのえる
- 軟らかくした餅を椀に盛り2を入れ
4を注ぎ入れて3を乗せる
材料(4人分)
- 丸餅4個
- 塩ブリ2切れ
- 鶏肉100g
- かき8粒
- 大根50g
- 人参50g
- かまぼこ1/3
- 三つ葉少々
- だし3カップ
- 塩、醤油適宜
※このページで紹介しているレシピは、一般的に伝わる
イメージで作っております。地域によって異なる場合があります。
お雑煮の主役であるお餅。
これには四角い角餅と丸い餅の2種類が
あることをご存知でしょうか。
大雑把に言って東日本は角餅、
西日本は丸餅文化。
お雑煮発祥の地・京都の食文化の影響を
強く受けた地域は主に丸餅を用います。


そのほかにも色々な
おもちレシピがあります
民俗学者(社会学博士)
1948年広島県生まれ。
早稲田大学第一文学部史学科卒業、同大学院史学専攻博士課程修了。
国立歴史民俗博物館・国立総合研究大学院大学 名誉教授。
おもな著書に『伊勢神宮と出雲大社ー「日本」と「天皇」の誕生』講談社、『民俗学とは何か』、『神社の起源と歴史』、『遠野物語と柳田國男』吉川弘文館、『政治の米・経済の米・文化の米』山川出版社※。(※2025年3月刊行予定)