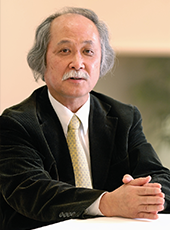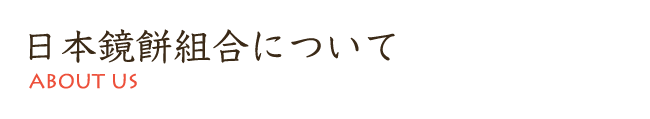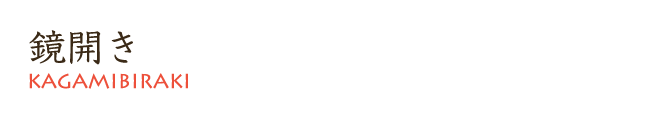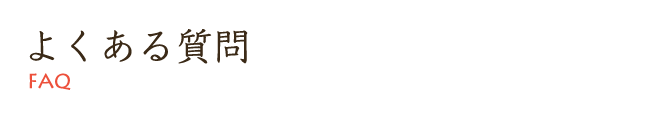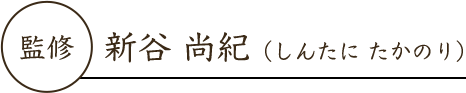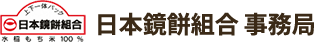鏡餅の飾りにはそれぞれ意味があり、また飾り方にも時代の流れにより変化したり、地域によって飾り方が異なる場合があります。
江戸時代、武家では、お正月に鎧(よろい)や兜(かぶと)を飾って、その前に供えた鏡餅を「具足(ぐそく)餅」と呼んでいました。縁起をかついで裏白、譲葉(ゆずりは)、橙(だいだい)、昆布、串柿、海老、などを豪華に飾りました。
今日では、簡略化され、半紙を敷いた三方(三方の側面に穴のある四角形の台)に載せ、橙(だいだい)、譲葉(ゆずりは)、昆布などを添えるのが一般的とされています。
また、地方によって飾り方が異なり、裏白(しだ)、串柿、干しするめを載せたり、四手(しで)を垂らすところもあります。
「一年の計は元旦にあり」といわれるように、日本人は一年の節目であるお正月をことのほか大切に考えています。
お正月の基本は、人々が年をとること、つまり年齢を一つ重ねることにあります。
お正月にお供えする鏡餅はその年に収穫された新米で作られます。その搗き固められた餅には清らかな米の霊力が宿ると考えられました。よって鏡餅は、年神様の宿る供物であるとか、年齢を重ねる生命力が宿るなどと考えられてきたのです。
ご不幸があった年のお正月には年賀状を出すのを控えるのが普通ですが、門松や注連飾りを控えるということはしません。お雑煮も食べますし、お年玉ももらえます。同様に、鏡餅もその年の健康と幸運を祈って供えると良いでしょう。
たとえご不幸があったとしても、生きている人間が正月に新しい年を取らない訳にはいきません。むしろ、元気で縁起の良い年にするためにも、鏡餅を供え、それをいただくことは大切だと考えます。


腰が曲がるまでの
長寿を祈ります。


木から落ちずに
大きく育つ
ことから、
代々大きくなって
落ちないという縁起物。


喜(よ)いことがやってくる
(嘉来)という意。
また、
財(たから)が
串で刺したように
集まるとも言われます。


よろこぶの
語呂合わせ。


古い葉とともに
新しい葉が次第に裏に
なり伸びてくるので、
久しく栄えわたる
縁起を担いで
います。
形が左右対称なので、
夫婦の相性を祝う意味も。


ゆでて干した栗の実。
勝栗の語呂で
縁起を担いでいます。


新しい葉が
大きくなってから
古い葉が落ちるので、
代々家系がうまく
つながって
ゆくことを
祈ります。


長寿の象徴と
されております。
民俗学者(社会学博士)
1948年広島県生まれ。
早稲田大学第一文学部史学科卒業、同大学院史学専攻博士課程修了。
国立歴史民俗博物館・国立総合研究大学院大学 名誉教授。
おもな著書に『伊勢神宮と出雲大社ー「日本」と「天皇」の誕生』講談社、『民俗学とは何か』、『神社の起源と歴史』、『遠野物語と柳田國男』吉川弘文館、『政治の米・経済の米・文化の米』山川出版社※。(※2025年3月刊行予定)